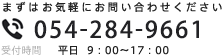事前に災害対応支援システムの整備を
各市町村は、災害発生後の混乱した状況の中で、避難所情報システムや罹災証明書の発行管理システムなど、どのようなシステムが必要なのかを「選択」「決定」し、これを使うために「訓練」し、現場に「実装」することを行っている。そのため十分に検討する時間も知識もないままに「選択」を求められる。結果的に、民間企業が社会貢献や善意で提供してくれたシステムの中から“良さそうなもの”を選択せざるを得ない状況である。
発災から一週間も経過すれば、電話とメモ書きで対応することに多くの職員は慣れ始める。この時点から新たに「選択」「決定」された情報システムを導入されても、現場で対応に当たる職員にとっては、業務量が増えると感じ、抵抗するものもある。
また、導入されたシステムがボトルネック工程とそれに関連する工程全体を最適化をするものでなければ、現場の対応を抜本的に効率化することにはならない。例えば、多くの行政職員が動員される建物の罹災証明書の発行においても、①現場での建物調査②調査記録の管理③罹災証明書の発行まで一気通貫したシステムである必要がある。②の現地調査の写真管理だけを見ても、住宅一棟に5、6枚の写真が必要になるため、調査対象の建物が1万棟にもなれば、5、6万枚の写真の管理が必要になる。さらにこれは③の罹災証明書の発行と関連付けられなければならないなど、災害対応工程全体が見えないと“良さそうなもの”あるいは現場担当者の個別の業務だけを見て判断すると効率性を高めることにはならない。
熊本県益城町の災害対策本部
2016年4月の熊本地震における熊本県益城町の災害対策本部では、各避難所など現場の状況はLINEを使って情報共有していた。情報が少ない発災直後は効果を発揮したが、情報量が多くなると物資のニーズ、各種要望などが羅列されかつ複数のグループが立ち上がったため、どの対応が完了したのか、未対応なのかなどのToDoの整理は容易ではなかった。また、LINEは、災害対策本部にいた職員が日常的に使っているコミュニケーションツールとして現場と本部の情報共有には一定の効果を発揮したが、災害対応の全体の工程管理はできないため、行政全体の災害対応工程の効率化にはつながらない。

- 益城町災害対策本部の様子
個別の市町村の意思決定と被災地全体の状況把握
大規模災害では、全体の状況把握による関係者の共通認識が必要であるため、これを支える災害対応支援システムは必須になるが、各種のシステムの「選択」「決定」「訓練」「実装」は各市町村の判断に委ねられている。従って、全ての避難所の状況把握においても市町村間で異なる避難所情報システムが導入されていれば、全体の状況把握はできない。
また、益城町に限らず多くの自治体には、被災地外から多くの応援職員が発災直後から駆けつけた。応援職員の有効活用においても、使用するシステムが標準化されていれば、応援自治体と被応援自治体でスムーズな連携がでるため、応援職員は効果的な活動ができる。
開発費の共同支出により17億円以上を捻出
静岡新聞データベースplus日経テレコンで「災害+システム+標準化」で検索すると166件がヒットする。2005年1月18日付静岡新聞朝刊に掲載された「来年度から内閣府が災害対策業務を標準化 自治体のシステムを整備」など、標準的な災害対応支援システムの開発の必要性は10年以上前から言われている。標準的な災害対応支援システムの開発において、技術・運用体制・開発費(維持管理費)を検討する必要がある。
わが国は、ますます貧乏になっていく時代であり、全国1,700の市町村の財源を集約し、国家として災害対応支援システムを開発し、これを全国で使い回し,進化させる仕組みが必要である。
単一の自治体が実際の災害で使うかどうかも不明なシステムに対し、数百万円を支出し開発しても、大したシステムはできず、防災訓練でも使われず、維持管理もできない。しかし、全国の各市町村が仮に100万円を支出し集めれば全国で17億円以上の開発費が集まるため大規模なシステム開発ができる。維持管理費についても、共同で支出すれば個別の自治体の負担は軽く、常に最新バージョンが利用できる状態で整備され、まれに直面する災害にも利用できる。
全国的に「利用」「更新(教訓をシステムに反映)」の実績が積み重なり、ヘビーユーザーが増えれば、米国のICSを参考にするものの、国際競争力の高い日本発の災害対応支援システムを輸出できる。